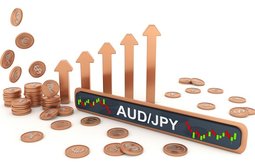優良不動産が不良資産に 法改正なども進みオーナー責任増大

あなたの不動産は不良資産?
優良資産だと思っていた不動産が、実は不良資産ということも多いです。
相続で一番厄介なものも不動産です。
次の記事の続きなので合わせてお読みください。
https://real-int.jp/articles/2920/
厄介な不動産
厄介な不動産には次のようなものがあります。
厄介な不動産
・耐震性能が低い建物
・売却が困難 評価が高いが売却困難
底地、借地
共有不動産
権利が複雑・税金が複雑
管理が難しい不動産
隣接地の所有者の確認がない測量
・トラブルを抱えた不動産
境界争いがある土地
不良賃借人がいる
・不動産事業が苦手な人が不動産事業をする
・マイナス資産の不動産
相続で取得したために破綻することもあります。
法改正や新しい裁判判決
最近、不動産について法改正や新しい最高裁の判例などが続き、年々オーナーに厳しくなっています。
優良資産だと思っていたものが突然不良資産になることもあります。
常識がどんどん変化しているので時代についていくことが大事です。
法改正や新しい判例
①地震で倒壊した責任はオーナー
②空き家にすると増税
③別荘の管理費を払わないと裁判で負ける
④相続が発生したら不動産登記が必要
①地震で倒壊した責任はオーナー
地震で建物倒壊するケースで
建物の瑕疵(かし・欠陥)が原因で倒壊した場合、
オーナーが損害賠償責任を負う可能性があります。
不可抗力による地震の場合、通常はオーナーの責任は問われませんが
建物の耐震性不足や、施工上の問題があった場合、
つまり、周りの建物が倒壊していないのに、その建物だけ倒壊したら
オーナーの責任となる可能性があるということです。
自分で建てたビルでなくて、他人から買ったビルや相続したビルでも同じです。
実際に、阪神淡路大震災の時、投資で買ったビルやアパートが倒壊し、
その責任をオーナーが負ったケースがあります。
代表的な裁判例:神戸地裁 1999年9月20日判決
物件:1964年築の賃貸用アパート(旧耐震基準)
震災:1995年 阪神・淡路大震災(震度7)
被害:アパートの1階部分が倒壊し、賃借人4人が死亡
判決:建物の設計・施工に瑕疵(安全性の欠如)があったと認定
オーナーに対して、約1億3,000万円の損害賠償責任を認めた
地震という自然力の寄与度を50%とし、損害額を半減して算定
②空き家にすると増税
空き家にして放置したことで、「特定空き家」に認定されると
固定資産税の軽減の特例が外れ、固定資産税が上昇します。
そして最大50万円の過料(罰金)が課される可能性もあります。
自治体からの改善措置を無視し続けると、最終的に行政代執行が行われる可能性もあります。
行政が所有者に代わって、強制的に空き家の解体や撤去ということも行われています。
解体費用は全額所有者負担です。
③別荘の管理費を払わないと裁判で負ける
別荘の管理費を払わなかったことで最高裁で負けた判決が出ました。
今後、これが判例となり、争いも増えるのでしょう。
使っていない別荘でも、高額な管理費でも支払う義務があるということです。
管理費用が高いために売却できない別荘もありますが、そのような物件も同じです。
④相続が発生したら不動産登記が必要
相続が発生したら不動産登記が必要になりました。
登記期限までに遺産分割協議ができずに共有登記して、共有が問題になることもあります。
押し付け合いになりがち
本人が優良だと思っていても相続人にとっては不良資産となり、相続人の間で不動産の押し付け合いになることが多いです。
不動産があることで相続争いが勃発することが多いということです。
特に借金がある投資用不動産は要注意です。
不動産投資という不良資産
不動産投資が他の投資と異なる点は、不動産投資とは不動産事業を営むことだということです。
不動産事業をしたくない人や不動産賃貸事業が苦手な人が投資用不動産を相続したり、取得することでトラブルになりやすいです。
不動産売買仲介や不動産売買コンサルをしている人は自分では不動産投資を避ける傾向があると思います。
不動産トラブルをよく知っていることが原因です。
解体費上昇中
場所や状態によって異なりますが、解体費は、ドンドン上昇して
木造一戸建ての解体費は数百万円で済まなくなっているケースもあります。
先送りは危険です。
建物にアスベストを使っていると解体費は高額になります。
アスベスト対策を無視した解体業者を使ったことで問題となったケースは多いです。
無謀な相続税対策
借金をして建物を建てて相続税を低減させるという相続税低減スキームを実行したことでローン支払いの方が賃料より高くなり、破綻するケースがあります。
事業性が低いエリア・賃料が低いエリアなのに、相続税対策を目的に建てるからです。
優良な資産である更地を不良資産にすることで評価を下げることを相続税対策といっているわけです。
もちろん、相続人にとっても不良資産です。
対策
①不良不動産は売却する
相続評価は高いものの実際に売却しようとすると安価でしか売れない不動産があります。
整形地であれば良いですが、不整形地や再建築不可の土地は特に売りにくいです。
底地や借地、共有不動産など権利が複雑な不動産も、相続税評価が高いものの実際の売価は下がります。
早めに売却したり、整理が必要です。
②共有は避ける
不動産を共有することが資産価値を低減する原因になるので共有は避けます。
最近、電車広告やファックスDMで次のようなチラシがあります。
「共有者と一切連絡取りたくない不動産買います。」という内容です。
相続で不動産を共有にして、もめているケースが多いということです。
もちろん、買い取り価格は安価になります。
③きちんと測量しておく
隣接地と境界問題がある土地は多いです。
測量図があっても、隣地の確認印があればよいですが、「現況測量図」のように測量しただけでは意味がないと思ってください。
4メートル以上の道路に2メートル以上接道していないと建築ができない土地になり、不動産価値が急減します。(接道義務違反)
現況測量図は接道義務を満たしていても、実際に隣接地の確認印をもらおうとすると接道義務を満たさないことも多々あります。
本人が亡くなったら、隣地所有者が境界線が違うと言い出すこともあるので、生前にきちんと測量し、隣地所有者の確認印を得ておくことが重要です。
④ 時間とお金をかけて処分
次のような物件は価格をゼロにしても引き取り先がないケースがあります。
市区町村に無償で引き取ってもらいたくてもできない
別荘で毎月の管理費が高く売却できない
解体が必要な古家があり、解体費の方が高額
山林 管理が大変
時間とお金をかけて処分が必要です。
まとめ
黙示録の時代は想定外の災害や事件が多発します。
不動産を筆頭に、全ての資産を見直す時です。
リテラシーを高めることが必須の時代です。
https://real-int.jp/articles/2813/